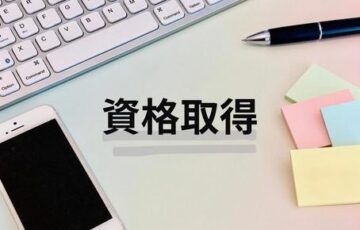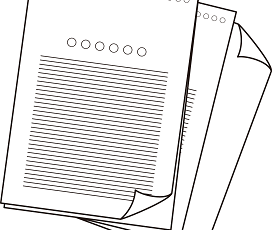皆様こんにちは。初めての方ははじめまして。
業界未経験の2月中途入社おじさんことスカイアーチの関口と申します。
前回見ていただいた方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
本文は著者が資格の取得の際に苦労した部分を紹介しております。
前回は「ITパスポート」という資格の取得の場合を紹介しましたが、
その資格について本文のテーマで一番紹介したかったところはもう前回ご紹介してしまいました。
そこで今回は「Linux」というOSを取り扱う資格である「LPIC LEVEL1」の前編、
「LPIC101」について一部ご紹介いたします。
<前振り>
※前振りは、興味のない方は飛ばして「本題」からお読みください。
前回と同じくLPICの正しい概略等は各々検索していただくとして、ざっくり説明させていただくと、
「Linuxを扱う上で、基本的な操作とシステム管理を行うための知識をつける資格試験」です。
この資格はLEVEL1、2、3とあり、LEVEL1と2は前後篇に分かれて試験を受け、
前後篇をともに取得すると資格を入手できるというものになっています。
で、これも前回と同じく、私が覚えにくい!と思った部分をピックアップいたします。
これから勉強を始める方に多少なりとも役立てたら嬉しく思います。
<本題>
では、本題に入ります。
今回は【パッケージ管理コマンド】についてご紹介します。
【パッケージ管理コマンド】
Linuxにはパッケージと呼ばれる物があります。
ざっくり説明すると、何かの機能(アプリとか、ホームページの作成の為に必要な機能とか)
を使用する際に、複数のプログラムやファイルが必要になる場合があります。
パッケージそのプログラムをまとめた物と考えていただけると分かりやすいかと思います。
(どうやらばらばらに配ってたプログラムを纏めたほうが使いやすいと、
この仕組みを考えた先人がいたようです。)
素敵!偉大!>
で、パッケージにはRed Hat系、Debian系といった開発思想による系統の違いがあります。
そしてその系統によってパッケージを取り扱うコマンド変わります。
しかも同じ系統でも目的によってコマンドとオプションが変わります。
やっている事は、パッケージのダウンロード、インストール、アップグレード、削除、情報確認等と
決して難しいイメージはないのですが、覚えるとなるととにかく面倒くさいわけです。
実際に使う際は、もしかしたら会社によって使う系統が決まってて一部しか使わなかったりするかもしれませんが、
試験で出る場合は話が別です。素人の私にはややこしいことこの上ないものでした。
で、どうやって切り抜けたかというと、試験ではそのパッケージが何系か?等は問われなかった為
単純にリストアップしました。
雑!>
雑ですが、ビジュアル化するだけで私は脳内での整理がかなり楽になりました。
苦手な方は是非お試しください。
暗記における図示化は基本ですが、それゆえに効果抜群です。おススメです!
基本所をノートにまとめた表を張りますので、もしよかったら使ってください。
(コマンドの内容は勉強してたら分かると思うので割愛します。)
| コマンドの目的 | Red Hat 系 | Debian 系 |
| 使用コマンド | yum及びrpm | apt-get及びdpkg |
| パッケージの管理 | ||
| リポジトリから パッケージのインストール |
yum install package名 | apt-get install package名 |
| パッケージファイルのインストール | rpm -ivh package名.rpm | dpkg -i package名.deb |
| パッケージの削除 | yum remove package名 | apt-get remove package名 |
| rpm -e packege名 | dpkg -r package名 | |
| アップデートがあるか確認 | yum check-update | apt-get -s upgrade |
| apt-get -s dist-upgrade | ||
| パッケージ全体のアップデート | yum update | apt-get upgrade |
| apt-get dist-upgrade | ||
| 特定のパッケージのアップデート | yum update package名 | apt-get upgrade package名 |
| apt-get dist-upgradepackage名 | ||
| パッケージ情報の参照 | ||
| パッケージを検索 | yum search string | apt-cache search string |
| リポジトリの全パッケージを表示 | yum list | apt-cache search . |
| インストール済パッケージの確認 | yum list installed | dpkg -l |
| パッケージについての情報を確認 | yum info package名 | apt-cache show package名 |
| rpm -qip package名.rpm | dpkg --info package名.deb | |
| インストール済のパッケージの情報確認 | rpm -qi package名 | dpkg -s package名 |
| パッケージに含まれるファイルを確認 | rpm -ql package名 | dpkg -L package名 |
| 特定のパッケージが依存するパッケージをリスト化 | rpm -qR package名 | apt-cache dependspackage |
良くある説明では、
「このコマンドだとこのオプションと組み合わせればこういう事が出来る」
と書かれていますが、私はごっちゃになって非常に苦労しました。
それでコマンドごとに覚えるのではなく、目的別に分けて覚える方向にしたわけです。
人によって会う合わないがあるともいますが、苦手に感じた方は是非ともお試しください。
本文の紹介はあくまで試験を切り抜ける方法としての紹介ですので、
実際に使う際はそのパッケージが何系なのか、自分が何系を良く使うのか、
を考えながらコマンドを使用するといいかもしれませんね。
今回はここまでです。
本文を最後までお読みいただき、ありがとうございました。
投稿者プロフィール
-
2016年2月入社の中途未経験おじさんです。
NY出張の際、スマートデバイスに目覚めたIT雑兵でもあります。
一通りのデバイスを購入した後に技適マークが無いことに気がついたと言う
悲劇のエピソードはいずれ語られるとか無いとか・・・
最新の投稿
 IoT2018年2月9日今更ながらスマートホーム化 ④Philips Hueで部屋の電気と連携 編
IoT2018年2月9日今更ながらスマートホーム化 ④Philips Hueで部屋の電気と連携 編 IoT2018年2月9日今更ながらスマートホーム化 ③スマートリモコンを使おう 編
IoT2018年2月9日今更ながらスマートホーム化 ③スマートリモコンを使おう 編 ニューヨーク2018年2月9日NYに出店する和食を食べてみた。
ニューヨーク2018年2月9日NYに出店する和食を食べてみた。 IoT2018年1月31日今更ながらスマートホーム化 ② IFFFTで連携 編
IoT2018年1月31日今更ながらスマートホーム化 ② IFFFTで連携 編